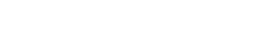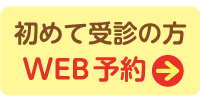- ホーム>
うつ病
うつ病
うつ病とは
憂うつな気分、興味の低下といった精神的な症状や、「眠れない」「食べられない」「疲れやすい」といった身体的な症状も現れ、今までの自分とは変わってしまったと思うような状態をいいます。
気持ち・行動の変化(精神症状)
抑うつ気分(何をしても気分が晴れない)、意欲・興味の減退(今まで好きだったことが楽しめない)、不安焦燥(イライラしてじっとしていられない)、後悔(悲観的な考えや過去の失敗が頭の中をぐるぐる駆け巡る)、仕事能率低下(仕事に集中できずミスが増える)といった状態になります。また、ひどくなると「このまま消えて、いなくなりたい」「死にたい」という思いが強まる希死念慮を認めます。
身体の変化(身体症状)
睡眠障害(寝つきが悪い・夜ぐっすり眠れない・朝早く目が覚める)、食思不振(食事が美味しくない・食べられない、易疲労感(疲れやすくて身体もだるい)、性欲低下、首・肩のコリ、頭重・頭痛などの症状が現れたりします。
「死にたいという気持ちになる」ことも含めて、これらはいずれもうつ病になったために現れる“症状”なのです。このような症状は、適切な治療をすることによって徐々によくなっていきます。
うつ病の症状
- 気が沈む。気が重い。
- 今まで好きだったことが楽しめない。
- テレビを見ても、音楽を聴いても楽しくない。
- 特に朝方は無気力で、何もする気が起こらない。
- 仕事の能率が上がらず、何をするのもおっくう。
- 人との会話・議論に集中できない。
- イライラしてじっとしていられない。
- お酒の量が増える。
- ボーッとして事故やケガをしやすい。
- 自分の人生がつまらなく感じる。
- このまま消えていなくなりたいと感じる。
- 夜ぐっすり眠れず、朝早く目が覚める。
- 食事が進まず、美味しいと感じられない。
- 疲れやすく、身体がだるい。
- 首すじや肩がこって仕方がない。
- 頭が重い感じがする。頭が痛い。
- 息がつまって、胸苦しい。
- ノドの奥に物がつかえている感じがする。
- 性的な関心がうすれ、性欲が低下する。
うつ病の原因
もともとの性格や考え方の傾向、環境(ストレスなど)に加え、体質・脳内にある物質の変化も関係しているといわれています。うつ病がなぜ起こるのかという、その原因や発症メカニズムについては、まだはっきりしたことはわかっていません。しかし、意欲や気分を調整する「セロトニン」や「ノルアドレナリン」といった神経伝達物質が十分に機能しなくなると、感情をうまくコントロールできなくなって、うつ状態に陥ってしまうといわれています。つまり、うつ病とは“精神的・肉体的疲労が続いていくうちに脳の中の「セロトニン」や「ノルアドレナリン」といった神経伝達物質の働きに異常を来してしまい、そのためにさまざまな症状が出現する病気”なのです。
うつ病の治療
●うつ病初期
うつ病初期でうつ病の症状が強い時には、抗うつ薬などによる「薬物療法」と「休養」を2本柱として、必要であればその他の治療法も組み合わせて行われます。
うつ病は、脳の中にある神経伝達物質の働きにまで異常を来している“病気”なので、「気の持ちよう」だけで治すことはできません。うつ病治療には、神経伝達物質のバランスを改善し、機能を回復させるきがある「抗うつ薬」と呼ばれるお薬などが必要になります。
また、うつ病を治療する上で「十分に休養をとること」も欠かせません。
なぜなら、うつ病になると判断能力や物事の処理能力が落ちてしまうため、普段なら簡単にできることができなかったり、いつもより何倍もの労力が必要になったりして、心身ともにとても疲れた状態になってしまっているからです。そのような時に無理をしてしまうと、心身ともに疲れ果ててしまい、症状をさらに悪化させてしまうことになります。
このため治療は、薬物療法で神経伝達物質のバランスの正常化をはかりながら、時間をかけて心身ともに休養し、元気が出てくるのを待つことを基本とします。また必要に応じて環境調整などもあわせて行っていきます。
うつ病初期で注意すること
うつ病になるとあらゆる機能・能力が低下し、また不安な気持ちが強くなって悲観的な考えから抜け出せなくなるため、いくら考えても進むべき正しい道が見出せなくなります。うつ病の時は本来の自分ではない状態なのです。うつ病の時にはできないと思うことの大部分は、回復すればできるようになるのです。したがって、このような時に人生の上での大きな決断をしてはいけません。うつ病の時の悩み事はいったん棚上げにして、回復してから考えるようにしましよう。
身体を休ませるために・・・
身体を休ませるためには、睡眠を十分にとることが必要です。ところがうつ病になると、症状として「眠れない」「眠りが浅い」「朝早く目が覚める」といった不眠症状が出ることが多いのです。不眠の対応は、うつ病治療においても非常に重要なので、不眠症状でお困りの方は一度、医師にお伝えください。
心を休ませるために・・・
心を休ませるためには、できるだけ「何もしない」「何も考えない」ようにしてください。「何もしない」ことに、罪悪感や後ろめたさを感じないでください。
なぜなら「何もしない」ことが“治療”だからです。この時期に「何もしない」「多くの睡眠をとる」ことは、心を休ませるためにとても重要になってきます。高齢者で転倒の危険性がある場合は別ですが、この時期に「何かをしなければ」と気持ちが焦るくらいならば、昼間でも何せずボーとできるように薬の力を使って鎮静をかける方が心の休養には有効です。
キチンとした休養がとれていれば、そのうちに自然に「何かをしたい」という気持ちになるので、その時までゆっくり待ちましょう。
●うつ病の回復期
うつ病の治療を始めると、徐々に症状がよくなってきます。この時期を「回復期」といいます。物事への関心や興味も少しずつ湧いてくるようになり、体調も徐々に回復し、自然にやりたいと感じることが出てきます。この時期になれば、回復の程度に合わせて1日の予定を立て、その予定にそって生活してみましょう。ただし、このような回復期には調子のよい時と悪い時の差が大きく、体調もまだ万全ではありません。
調子がよい日についやり過ぎてしまうと、その疲れがうつ症状を悪化させる原因となってしまいます。どの程度のことをしたらどの程度疲れるかを体験しながら、無理のない範囲で予定を立てるようにしましょう。この時期のポイントとして、調子に波があることを理解し、できない日があっても落ち込まず、できる範囲のことを段階的に少しずつ増やしていくことでしょう。薬物療法については、引き続き抗うつ薬などの治療を続ける必要があります。
回復期の過ごし方
- 調子の良し悪しに一喜一憂しない。
- 調子が悪い日があっても、うつ病初期の深刻な苦しさには至らず、また苦しい時間も長くは続かないことを理解する。
- 調子の波の変動が大きいため、良くなったり、悪くなったりしながら、徐々に良くなる経過をたどることを理解する。
- やりたいと感じることを、無理のない範囲で行う。
- その時点で無理なくできること(テレビを見る、漫画を読む、音楽を聴く、散歩をする)をやり、どの程度のことをしたらどの程度疲れるかを確認していく。
- 活動の内容や範囲に波があっても落ち込まず、ゆっくり段階的に増やしていく。
●うつ病の維持期
その後も治療を続けていると、うつ病の症状はさらに回復してきますが、うつ病がやっかいなのは、いったんよくなっても再び症状が出現したりする「再燃」と、しばらく経ってからまたぶりかえす「再発」をしばしば認めるためです。そのため、『治った』と感じてもすぐに抗うつ薬の服用をやめたりせず、「再燃」や「再発」を防ぐため、抗うつ薬の量を加減しながら薬物療法を続けていきます。この段階を「維持期」といいます。
このようにうつ病には、いくつかの段階を経ながら、徐々に治っていく病気です。あせらず一歩ずつ階段をのぼっていくように治療のゴールを目指しましょう。
[ページトップへ]